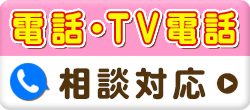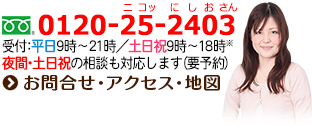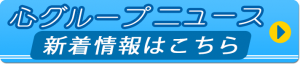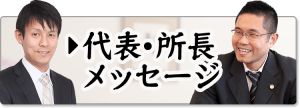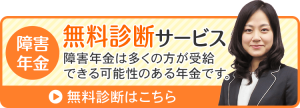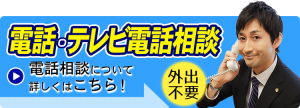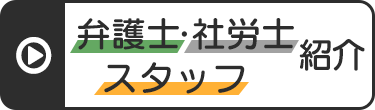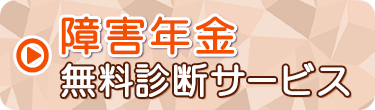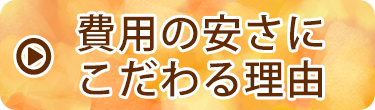障害年金における障害認定日について
1 障害認定日とは?
障害認定日とは、障害の程度を判断する日のことです。
症状が一定期間続いていたとしても、障害認定日が到来していなければ、障害年金の請求はできません。
障害認定日が到来すると、障害認定日の時点で障害等級に該当するか審査してもらう、認定日請求を行うことができます。
2 障害認定日の原則と例外
障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月を経過した日です。
ただし、例外的に、1年6か月よりも前に症状固定したと認められる場合にはその日が障害認定日となります。
また、20歳前に初診日がある場合にも原則と異なります。
この場合、20歳の誕生日の前日と、初診日から1年6か月後経過した日のうちいずれか遅い方が、障害認定日となります。
3 障害認定日の特例的な取り扱い
障害認定日の原則や例外に関わらず、一定の事由がある場合には、1年6か月を経過するよりも前の日を障害認定日とします。
例えば、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合には、挿入置換した日、人工透析療法を始めた場合には、透析開始日から3か月を経過した日、手足を切断した場合には切断した日、遷延性植物状態の場合にはその状態に至った日から3か月を経過した日以降に、医学的観点から機能回復がほとんど望めないときなどが挙げられます。
障害認定日が早く到来すれば、それだけ早く障害年金を受給できることになるため、特例的な取り扱いがされる場合かどうかを必ず見落とさないようにしなければなりません。
4 弁護士または社会保険労務士にご相談ください
障害年金の申請をお考えの場合、障害認定日を正しく把握しておく必要があります。
障害認定日には原則、例外、特例的な取り扱いがあるだけでなく、いつの時点が初診日となるかも正しく把握し、提出書類で証明しなければなりません。
しかし、初診日や障害認定日の把握が容易でないことが多いため、障害年金の申請をお考えの方は、障害年金に精通した弁護士または社会保険労務士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金に関する診断書の料金
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- 障害年金における障害認定日について
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病と障害年金3級
- 高次脳機能障害で障害年金を受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺線維症で障害年金を受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 肝硬変で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒500-8833岐阜県岐阜市
神田町9-4
KJビル4F
0120-25-2403